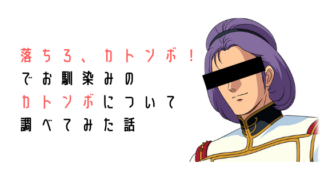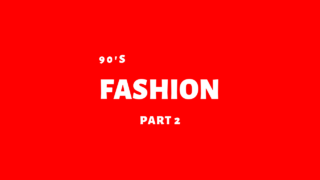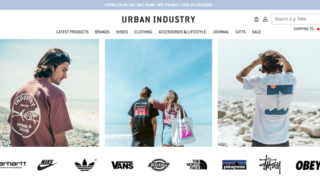あの頃の熱狂を再び!90年代B系ファッションブランド「Ecko Unltd.」「FUBU」など懐かしのブランドは今?
こんにちは
近年、ファッション業界で巻き起こる『90年代リバイバル』の波。
特にストリートシーンでは、当時の空気感をまとったアイテムが再注目されています。そのルーツを探ると、欠かせないのが『90年代B系ファッションブランド』の存在です。
この記事では、当時のファッションキッズを熱狂させたEcko Unltd.、FUBU、KARL KANIといった伝説のブランドたちに焦点を当てます。彼らがどのようにしてストリートの象徴となり、そして現在、どのような進化を遂げているのか?あるいは、もう手に入らない幻の存在となってしまったのか? 今のファッションにも通じる彼らの魅力と、手に入れる方法まで、余すことなくお伝えします。
かつてB系と呼ばれたファッションブランドたち
Clench
クレンチ
画像が見つからないです…
1994年にアメリカ・ニュージャージー州に設立。
2006年『CLH』にブランド名変更。
公式は見つけれませんでしたが、まだあるっぽいですね。
高校生の時に雑誌の通販ページにあったベロアセットアップに憧れました。
ライオンマークですが、プジョーみたいなマークもあったようななかったような…
Ecko Unltd.

エコーアンリミテッド
1993年にデザイナーMarc Eckoによって設立。
自身の名前である『Marc Ecko』というハイエンドブランドも立ち上げている。
『Ecko Unltd.』はサイのマークで『Marc Ecko』はハサミのマーク
サイとハサミの関係性はいかに!?
生き残ってました。
このサイのマーク見た事ある人って多いかと思います。
このジャンルの服で初めて買ったブランドなので残ってるのは素直に嬉しい。
enyce

エニーチェ
1996年にMeccaのデザイナーらが独立して立ち上げられたブランド。立ち上げ当初はイタリアのFila傘下でのスタート。
2003年にLiz Claiborne社に売却されていた。
その後、2008年にPuff Daddyが買収。
ちょっと前だとトップページのみのHPはあったんですけど、見れなくなってます。
もう無いっぽいですね。
ちなみにブランドの語源はイタリア語で”NYC”の発音がen-y-ceという事から。
FUBU

フーブ
1992年にニューヨークで創立。
地元の帽子屋で好きな帽子を見つけられなかった創立者の一人であるDaymond JOHNが自宅でオリジナルの帽子を作り始めた。
ブランド名は”For Us, By Us”(我々のための、我々による)の頭文字から。
その後、韓国のサムスンに買収されちゃってます。
まだ残ってた!!
横浜ビブレにお店があったのは何年前だろうか…
個人的にファットアルバートが好きだったなぁ。今見るとアントニーに似てる気がしないでもない。

Johnny Blaze
ジョニーブレイズ
1997年に創立。
1998年2月、ラスベガスでショーを発表し、アーバンストリートスタイルを提案。
広告塔にNELLYを使ってたような気がしないでもない。
もう無くなってるっぽいですね。悲しみ
ロゴ画像すら見つかりませんでした。トホホ
ちなみにJhonny Blazeで検索するとゴーストライダーが出てくるよ!
関係ないけど、セントルイス勢『Nelly、Murphy Lee、Chingy、J-Kwon、Prince EA』は未だにヘビロテするくらい好き。
今はStevie Stoneが一押しです。
KARL KANI

カールカナイ
1989年ブルックリン出身のプエルトリコ系アメリカ人であるファッションデザイナーCarl Williamsによって創立。
ブランドネームにあるKaniは”Can I?”から。
“Can I do it? Can I build a fashion empire? Can I become the ‘Ralph Lauren of the streets’?”
『やれるのか?ファッション帝国を築くことはできるのか?ストリートファッション界のラルフローレンになれるのか?』という事に由来している。
ざっくり言うと『やれるのか、オイ!』って事
多分見た事ある人はかなり多いと思うブランドの一つ。
めっちゃ残ってるし、なんかオサレだし。普通に欲しいし。
僕のKANIのイメージはシャカシャカのセットアップです。
MARITHE + FRANCOIS GIRBAUD

マリテフランソワジルボー
1964年にフランソワ・ジルボーとマリテ・ジルボー夫妻が創業。
当初はパリとビバリーヒルズに展開。
2013年に倒産し、一部店舗は閉店になった。
これは当時めちゃくちゃ流行った記憶があります。
テープの色の種類がたくさんあって、僕は赤と緑を持ってました。
そもそもストリートファッションでは無いってとこが面白い。
JuvenileやB.G.やらサウス勢も履いてるけどGrand Pubaよりもずっと後の2000年代だし、ゴリゴリ90年代のGrand Pubaが火付け役のような気が。
JuvenileのNolia ClapのMVに出てるB.G.がツボ過ぎて、腕にギブスを巻きたくてたまらなかったのを覚えてます。
MECCA USA

メッカUSA
1994年にニューヨークで設立。
ヒップホップとその誕生地であるニューヨークからインスピレーションを得たアーバンウェアのパイオニア。
お手頃な価格でおしゃれなデザインのおしゃれな服を消費者に提供するというコンセプトのもとに設立されており、メンズ、レディース、子供服はすべてこのブランドの参入の影響を受けたらしい。
正直ブランド名は宗教的に大丈夫なのか?とは思う。
Facebookページですが、まだ残ってるようです。
Notorious BIGがMVで着ていたのを覚えているのですが、どのMVだったか全く思い出せない。年かしら?
PellePelle

ペレペレ
1978年にマーク・ブキャナンが創業。
創業当初は、型にはまらない色とインパクトのあるアクセントの組み合わせで、非常に詳細できわどく、斬新な革製品を中心に展開してきました。
1990年代初期にブランドを拡大し、男性向けライフスタイルブランドとしての地位を確立した。
公式はあったのですが、コレクションは2017年までしかありませんでした。

Pelle Pelle x Wu-Tangのコラボのセットアップがめちゃくちゃカッケー!
普通に欲しいな、これ…
Pepejeans

ペペジーンズ
1973年にケニヤ出身のNitin、Arun、MilanのShah3兄弟がウエストロンドンの「ポートベロー・ロード」にジーンズブランドを創業したのが始まり。
ペレペレと同様にめちゃくちゃ歴史の長いブランドである。
この記事を読んでいる人の4割くらいはこのブランド名を見て『ペペ…だと…?』って思ったに違いない。
そう、オレンジキャップでおなじみのアイツである。
最初に言っておく、全く関係ない。ジーンズのペペはロンドン、ロー〇ンのペペは中島化学産業株式会社さんです。お世話になります。
かなり脱線しましたが、
このペペジーンズ実はアクネジーンズ、スーパーファイン、ヌーディージーンズ、G-STARなどと肩を並べる代表的なヨーロピアンジーンズブランドである。
さっき勘違いしてニヤニヤした諸兄は、しっかりと反省するように!
公式を見るとすごくイメージとは違うオサレな感じとなっております。
なにが『代表的なヨーロピアンジーンズブランド』やねん!とか思ってすいませんでした。
僕の知ってるPepejeansはもうありませんでした…
あとがき的なやつ
いかがでしたでしょうか? 90年代B系ファッションは、単なる流行ではなく、当時のカルチャーと密接に結びついた、まさに『生き様』を表現するスタイルでした。この記事を通じて、あなたの青春時代の思い出が蘇ったり、あるいは新たなファッションの発見があったなら幸いです。
ぜひコメント欄で、あなたが一番思い出に残っている90年代B系ブランドや、当時のエピソードを教えてください! あなたのコメントが、次の記事のインスピレーションになります。
これからもShoeRemakeでは、スニーカーやファッションに関するディープな情報を発信していきますので、どうぞお楽しみに!
今回の記事は『その1』となっております。『その2』はこちら
それではまた